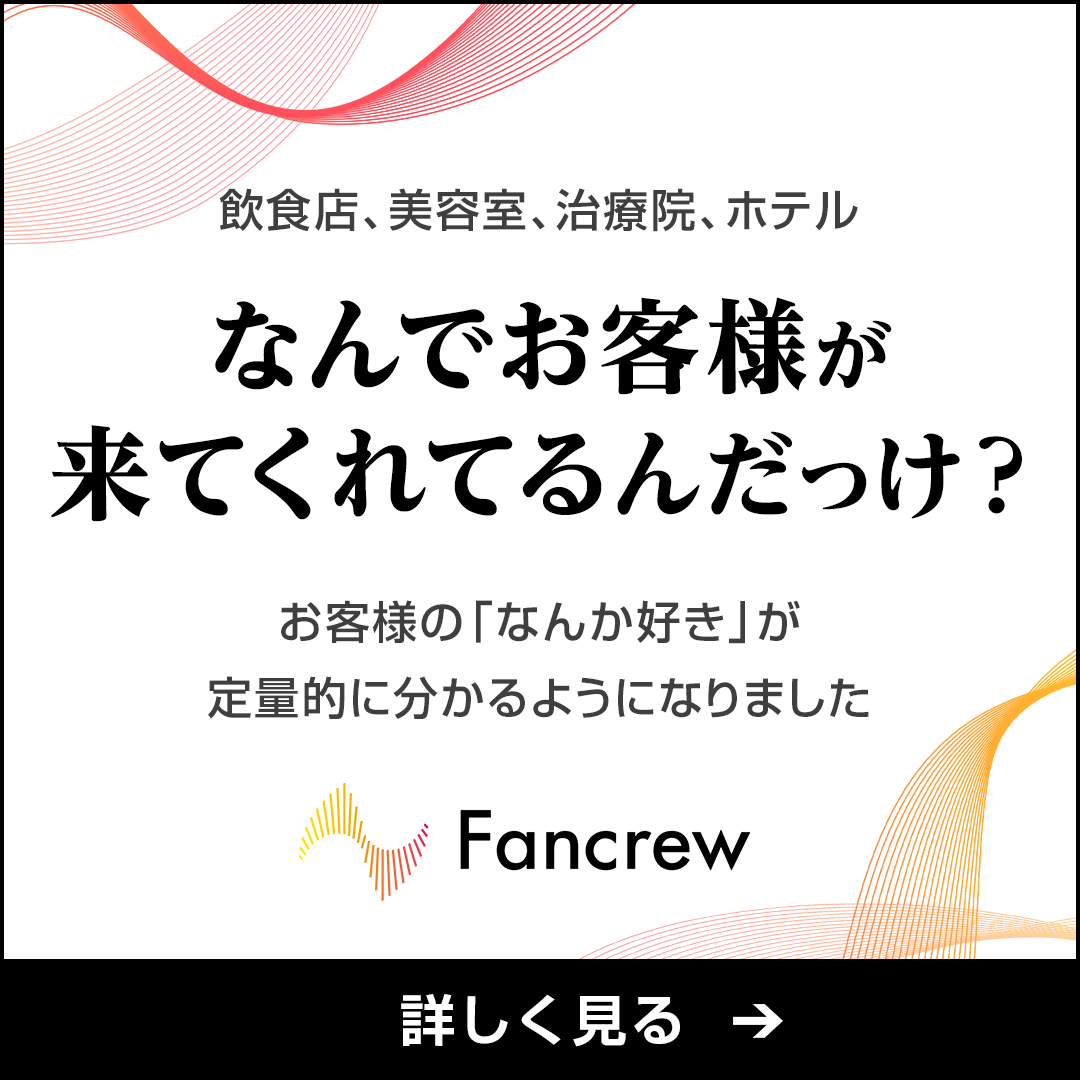エンゲージメントとモチベーションは、どちらも従業員の意欲に関わる言葉ですが、その意味合いは異なります。
この2つの概念を正しく理解することは、組織の生産性向上や人材定着に不可欠です。
この記事では、エンゲージメントとモチベーションの違いとは何か、そして従業員満足度との関係性や、それぞれを高めるための具体的な施策について解説します。
エンゲージメントとモチベーションの根本的な違いを解説
エンゲージメントとモチベーションの根本的な違いは、意欲の方向性にあります。
モチベーションが個人の目標達成に向けた内的な動機であるのに対し、エンゲージメントは組織の目標達成への貢献意欲という、組織と個人の双方向の関係性を示す概念です。
つまり、モチベーションとエンゲージメントとの違いは、個人完結の意欲か、組織とのつながりの中で生まれる意欲かという点にあります。
エンゲージメントとは組織と個人の成長に向けた強いつながり
エンゲージメントとは、従業員が所属する組織に対して抱く「貢献意欲」や「愛着心」を指します。
これは、企業の理念やビジョンに共感し、仕事に誇りを持ち、組織の成功のために自発的に力を尽くしたいというポジティブな状態です。
従業員のエンゲージメントが高い組織では、従業員と企業が対等な立場で互いに成長し合える関係性が構築されています。
単に会社に所属しているだけでなく、組織と個人が一体となって、共通の目標に向かって進んでいる状態が、エンゲージメントの高い状態と言えます。
モチベーションとは目標を達成するための個人的な意欲
モチベーションとは、人が目標に向かって行動を起こし、それを維持するための心理的なエネルギー、つまり「やる気」や「動機付け」を指します。
モチベーションには大きく分けて2種類あり、一つは仕事そのものへの興味や探求心、達成感から生まれる「内発的動機付け」です。
もう一つは、報酬や昇進、他者からの評価といった外部からの働きかけによって生まれる「外発的動機付け」です。
これらは個人の目標達成やパフォーマンスに直接影響を与えますが、そのエネルギーが必ずしも組織の方向性と一致するとは限りません。
エンゲージメントと従業員満足度の違いは「貢献意欲」の有無
エンゲージメントと従業員満足度の違いは、企業への「貢献意欲」を含むかどうかという点にあります。
従業員満足度は、給与や福利厚生、労働環境といった待遇面に対する従業員の満足度を示す指標であり、働きやすさや居心地の良さを表します。
一方で、満足度が高くても、必ずしも業績向上に貢献する行動につながるとは限りません。
エンゲージメントは、この満足度に加えて、組織に貢献したいという自発的な意欲を含む概念であり、従業員満足度やロイヤリティとの関係の中でも、より能動的な関与を示す点で異なります。
従業員のエンゲージメントを高めることで得られる3つのメリット
従業員のエンゲージメントを高めるために様々な施策を推進することは、企業に多くのメリットをもたらします。
エンゲージメントが高い状態では、従業員は自社の事業や自身の仕事に誇りと情熱を持ち、自発的に組織へ貢献しようとします。
これにより、個人のパフォーマンス向上だけでなく、組織全体の活性化や持続的な成長が期待できます。
生産性が向上し企業の業績アップに貢献する
エンゲージメントが高い従業員は、自身の仕事が組織の成功にどう結びつくかを理解しているため、日々の業務に対して高い当事者意識を持っています。
彼らは与えられた業務をこなすだけでなく、より良い成果を出すために自発的に工夫し、課題解決に取り組みます。
このような主体的な行動は、一人ひとりの生産性を高めるだけでなく、チームや部署全体のパフォーマンス向上にも寄与し、最終的に企業全体の業績アップという形で成果に結びつきます。
優秀な人材の定着率が向上し離職を防止する
エンゲージメントが高い社員は、組織に対して強い愛着と帰属意識を持っています。
企業のビジョンや価値観に共感し、自身の成長と組織の成長が連動していると感じられるため、働くことに喜びや誇りを感じます。
このようなポジティブな関係性は、待遇面だけでなく、働きがいという側面から従業員の満足度を高めます。
結果として、より良い条件の他社へ移るという選択肢が生まれにくくなり、組織にとって貴重な優秀人材の流出を防ぎ、定着率の向上につながります。
従業員の自発的な行動や発言が増加する
エンゲージメントが高い従業員は、自身の役割に責任とやりがいを感じ、組織の一員としての自覚が強まります。
そのため、指示を待つのではなく、自ら組織の課題を発見し、その解決策を提案するといった自発的な行動が増加します。
また、会議の場などでも積極的に意見を発信するようになり、組織内のコミュニケーションが活性化します。
このような従業員一人ひとりの主体的な関与は、新たなアイデアやイノベーションを生み出す土壌となり、組織の持続的な成長を支える原動力となります。
従業員のモチベーションを高めることで得られる3つのメリット
従業員のモチベーション向上は、組織に多くのプラスの効果をもたらします。
個人の仕事に対する熱意を引き出すことは、エンゲージメント、モチベーションの双方を高める上で重要です。
モチベーションが高い従業員は、目標達成に向けてエネルギッシュに行動するため、個人の成長だけでなく、職場全体の雰囲気にも良い影響を与え、組織の活性化につながります。
個人の業務パフォーマンスが最大化される
モチベーションが高い従業員は、自身の業務に対して高い集中力を発揮し、主体的に取り組みます。
目標達成への意欲が強いため、困難な課題に対しても粘り強く、質の高い成果を生み出すことができます。
このような状態は、仕事に没頭し、やりがいを感じている「ワーク・エンゲイジメント」にも通じます。
結果として、従業員一人ひとりの生産性が向上し、個人のパフォーマンスが最大化されることで、チームや組織全体の目標達成に大きく貢献します。
スキルアップなど従業員の自己成長を促進する
モチベーションが高い従業員は、現状に満足することなく、常に自身の成長を求める傾向があります。
目標を達成するため、あるいはより高いレベルの仕事に挑戦するために、自発的に必要な知識やスキルを学ぼうとします。
資格取得のための学習や、業務に関連するセミナーへの参加など、自己投資を惜しみません。
このような自己成長意欲は、個人の能力を高めるだけでなく、組織全体の知識資本を豊かにし、将来の事業展開を支える人材育成にもつながります。
職場全体の活気が生まれ雰囲気が良くなる
モチベーションが高い従業員の前向きな姿勢や熱意は、周囲の同僚にも伝播します。
目標に向かって意欲的に取り組む姿は、他の従業員にとって良い刺激となり、チーム全体の士気を高める効果があります。
活発な意見交換や協力体制が生まれやすくなるため、職場全体のコミュニケーションが円滑になり、雰囲気が良くなります。
このような活気ある職場環境は、新たな挑戦を歓迎する風土を醸成し、組織全体の生産性向上に寄与します。
従業員のエンゲージメントを高めるための具体的な施策
従業員のエンゲージメントを高めるためには、多角的なアプローチが求められます。
まず、エンゲージメントサーベイなどを活用して組織の現状を正確に把握し、課題を特定することが重要です。
その上で、企業の理念浸透、コミュニケーションの活性化、公正な評価制度の構築といった施策を、一貫性を持って継続的に実行していく必要があります
企業の理念やビジョンを明確に伝え浸透させる
従業員のエンゲージメントを高める上で、企業の理念やビジョンへの共感は不可欠な要素です。
経営層が自社の存在意義や目指す方向性を明確な言葉で示し、繰り返し発信し続けることが重要となります。
例えば、エンゲージメントを構成する7つの要素の中にも、理念や戦略の理解が含まれています。
全社会議や社内報などを通じてメッセージを伝えるだけでなく、日々の業務と理念がどのようにつながっているのかを管理職が具体的に示すことで、従業員は自身の仕事の意義を実感し、組織への貢献意欲を高めます。
1on1ミーティングなどを通してコミュニケーションを活発にする
エンゲージメントの向上には、良好な人間関係、特に上司と部下の信頼関係が大きく影響します。
定期的な1on1ミーティングの実施は、この信頼関係を構築するための有効な手段です。
業務の進捗確認だけでなく、部下のキャリアプランや悩み、関心事について対話する時間を設けることで、上司は部下への理解を深め、適切なサポートを提供できます。
ミーティングの内容を簡単なレポートとして記録し、継続的な成長支援に役立てることで、従業員は会社から大切にされていると感じ、エンゲージメントが向上します。
働きがいを感じられる公正な人事評価制度を整える
従業員が自身の貢献を正当に認められていると感じることは、エンゲージメントを高める上で極めて重要です。
そのためには、透明性と公平性の高い人事評価制度の構築が不可欠となります。
評価基準を明確に公開し、誰がどのような成果を上げれば評価されるのかを全従業員が理解できる状態にすることが求められます。
また、期末の評価だけでなく、定期的なフィードバックを通じて、従業員の成長を支援する姿勢を示すことも大切です。
成果だけでなく、プロセスやチームへの貢献なども含めて多角的に評価する仕組みが、従業員の納得感を高めます。
従業員のモチベーションを引き出すための具体的な施策
従業員のモチベーションを引き出すには、個人の価値観や意欲の源泉が多様であることを理解し、画一的ではないアプローチを取ることが重要です。
例えば、営業成績のランキングを公表するといった外発的な動機付けが有効な場合もあれば、内発的な動機付けに働きかける方が効果的な場合もあります。
個々の従業員に合わせた目標設定や、適切な裁量権の付与、公平な報酬制度などを組み合わせることが求められます。
本人のキャリアプランに沿った目標を設定しサポートする
従業員のモチベーションを高めるには、会社が設定した目標を一方的に課すのではなく、本人のキャリアプランや成長意欲と結びつけることが効果的です。
上司が1on1などの機会を通じて部下の目指す将来像をヒアリングし、それを踏まえた上で、挑戦しがいのある目標(例えば10段階評価で8を目指すような少しストレッチした目標)を共に設定します。
そして、目標達成に向けて必要な支援を継続的に行うことで、従業員は仕事を通じて自己実現できると感じ、内発的なモチベーションが高まります。
成果に見合った正当な報酬やインセンティブを付与する
従業員の努力や成果に対して、正当な報酬で応えることは、モチベーションを維持・向上させるための基本的な要素です。
特に、個人の成果が明確に測定できる職種においては、業績に連動したインセンティブ制度が強力な動機付けとなります。
重要なのは、報酬制度の公平性と透明性を確保することです。
評価基準や報酬の決定プロセスが明確でなければ、従業員は不公平感を抱き、かえってモチベーションを低下させる原因にもなりかねません。
誰もが納得できる仕組みを構築することが不可欠です。
従業員の裁量権を広げて仕事の主体性を尊重する
従業員に仕事の進め方や意思決定に関する裁量権を委譲することは、内発的モチベーションを引き出す上で非常に有効な手段です。
自分で考えて仕事を進める経験は、従業員に当事者意識と責任感を芽生えさせ、仕事へのやりがいを深めます。
上司が細かく指示を出すマイクロマネジメントは、従業員の主体性を奪い、モチベーションを削いでしまう可能性があります。
一定のルールの中で、従業員が自らの判断で行動できる範囲を広げることで、自律的な働き方を促し、成長を支援する姿勢が重要です。
まとめ
エンゲージメントとモチベーションは、共に従業員の意欲を示す指標ですが、その性質は異なります。
モチベーションが個人の目標達成に向けた「動機付け」であるのに対し、エンゲージメントは組織の成功への自発的な「貢献意欲」であり、組織と個人の強いつながりを示す概念です。
モチベーションは個人のパフォーマンスを直接的に高め、エンゲージメントはそれに加えて、組織全体の生産性向上や人材定着に寄与します。
両者は相互に影響し合う関係にあり、企業の持続的な成長のためには、それぞれの特性を理解し、自社の課題に応じて適切な施策を組み合わせて実践していくことが求められます。