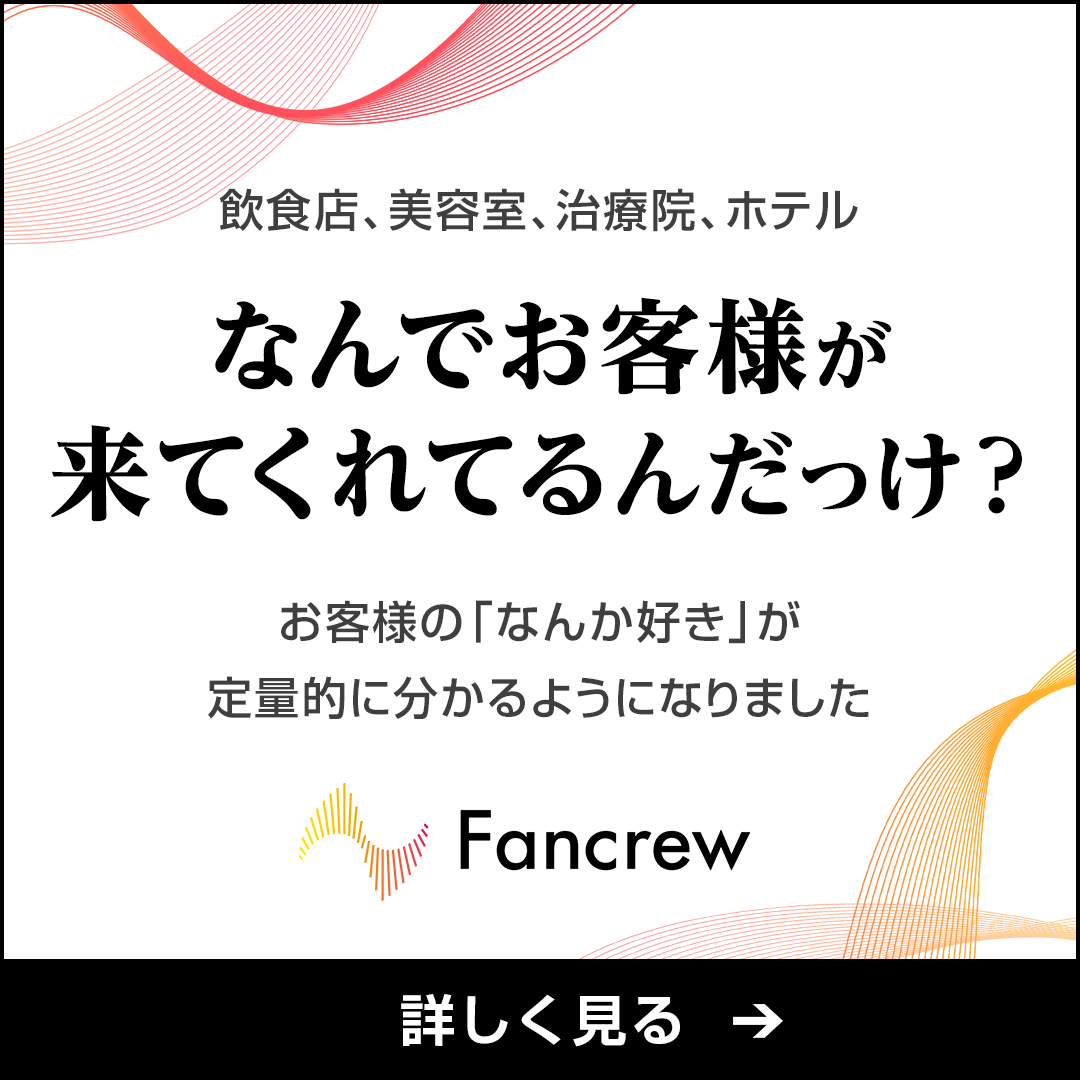企業のブランディングにおいて、自社ブランドがターゲット顧客にどの程度認識されているかを把握することは、マーケティング戦略の根幹をなします。
ブランドの現状を客観的に評価し、今後の方向性を定めるためには、認知度調査が不可欠です。
この記事では、ブランディング調査の中でも特に重要な認知度調査の目的や具体的な手法、すぐに使えるアンケートの設問例、さらには調査結果を戦略に活かすための実践的なノウハウを解説します。
ブランディング調査における認知度調査とは?
ブランディング調査における認知度調査とは、自社の製品やサービス、企業ブランドが、ターゲットとする市場や消費者層にどれくらい知られているかを測定する活動です。
単にブランドの知名度が高いか低いかを調べるだけでなく、消費者がブランドに対してどのようなイメージを持っているか、競合他社と比較してどのような位置づけにあるかを客観的なデータに基づいて把握することを目的とします。
これにより、ブランドの健康状態を定量的に評価し、マーケティング戦略の立案や修正に役立つ重要な示唆を得ることができます。
ブランドの認知度を調査する3つの目的
ブランド認知度調査は、漠然と行うのではなく、明確な目的意識を持って実施することが重要です。
主に「現状のブランドポジションの把握」「マーケティング施策の効果測定」「競合他社との比較」という3つの大きな目的があります。
これらの目的を事前に設定することで、調査設計が具体的になり、得られたデータをより効果的に戦略へ活かすことが可能となります。
調査を通じて、ブランドが抱える課題や機会を浮き彫りにし、次のアクションへと繋げます。
現状のブランドポジションを正しく把握するため
自社ブランドが市場においてどのような立ち位置にあるのか、ターゲット顧客にどの程度浸透しているかを客観的な数値で把握することが、認知度調査の第一の目的です。
多くの企業は自社ブランドに対して主観的なイメージを持っていますが、実際の消費者の認識とは乖離があるケースも少なくありません。
調査によって、ターゲット層における認知率やブランドイメージ、さらには意図しない層にまで浸透しているかといった実態を正確に把握することで、思い込みに基づいた戦略ではなく、事実に基づいた的確なブランド戦略を立案するための土台を築くことができます。
マーケティング施策の効果を測定するため
広告キャンペーンやプロモーション活動など、多大なコストを投じて実施したマーケティング施策が、実際にどの程度ブランドの認知度向上に貢献したのかを評価する目的で調査が行われます。
施策実施の前後で認知度を比較測定することで、その効果を定量的に可視化することが可能です。
これにより、施策の有効性を判断し、ROI(投資対効果)を評価する際の客観的な指標となります。
また、どのチャネルからの認知が効果的であったかを分析することで、将来のメディアプランニングや予算配分の最適化にも繋げられます。
競合他社との立ち位置を比較するため
自社ブランドの認知度を測定するだけでは、その数値が市場全体の中で高いのか低いのかを判断することは困難です。
そこで、主要な競合ブランドを調査対象に含め、同じ指標で比較することで、市場における自社の相対的なポジションを明確に把握します。
競合と比較して認知度で勝っている点や劣っている点、ブランドイメージの違いなどを分析することで、自社の強みと弱みが浮き彫りになります。
この分析結果は、差別化戦略の立案や、自社が目指すべき独自のポジションを確立するための重要なインサイトを提供します。
ブランド認知度を測る2つの重要な指標
ブランドの認知度を正確に測定するためには、単に「知っているか」を問うだけでは不十分です。
消費者の記憶にどれだけ強く、深くブランドが刻まれているかを測るためには、主に2つの重要な指標が用いられます。
それは「純粋想起」と「助成想起」です。
これらは、ブランドの知名度の「深さ」と「広さ」をそれぞれ示すものであり、両方の側面から認知度を分析することで、ブランドの浸透度をより立体的に理解することが可能になります。
ブランド名を自発的に思い出せるか【純粋想起】
純粋想起とは、「(製品カテゴリ)といえば、どんなブランドを思い浮かべますか?」といったヒントのない質問に対して、消費者が自発的に特定のブランド名を思い出すことができるレベルの認知度を指します。
特に、最初に思い浮かべられるブランド(第一想起)は、そのカテゴリにおいて非常に強い存在感を持ち、消費者が購買を検討する際に最初に候補となりやすいことを示します。
純粋想起は知名度の深さを測る指標であり、この数値が高いほど、強固なブランドが構築できている状態といえます。
ヒントを与えられてブランドを認識できるか【助成想起】
助成想起(aided awareness)は、ブランド名やロゴ、パッケージなどを提示された際に、「このブランドを知っている」または「見聞きしたことがある」と認識できるレベルの認知度を意味します。
これは、ブランドの知名度の広がりを示す指標です。
純粋想起には至らないものの、何らかの形でブランドに接触した経験があることを示唆します。
市場に参入したばかりの新しいブランドや、ニッチな市場をターゲットとするブランドにとっては、まずこの助成想起率を高め、存在を知ってもらうことが最初のステップとなります。
ブランド認知度調査の代表的な手法3選
ブランド認知度を測る調査手法には選択肢があります。
どの手法を選ぶかは、調査の目的、対象者、予算、期間などによって異なります。
代表的な手法として、
- 広範囲の対象者に効率的にアプローチできる「インターネットリサーチ」
- 個人の深層心理に迫る「インタビュー調査」
- 特定のエリアの生活者の声を直接聞く「街頭調査」
が挙げられます。
これらの手法は、アンケート調査を基本としながらも、それぞれに特徴と利点があり、目的に応じて使い分けることが重要です。
幅広い層にアプローチできる「インターネットリサーチ」
インターネットリサーチは、オンライン上のアンケート調査システムを利用してデータを収集する手法です。
地理的な制約なく、短期間かつ比較的低コストで大規模なサンプルを集めることが可能なため、ブランド認知度調査で最も一般的に用いられます。
年齢や性別、居住地などの属性で対象者を絞り込むことも容易であり、全国規模での認知度やターゲット層における浸透度を定量的に把握したい場合に適しています。
ただし、インターネットを利用しない層にはアプローチできないという限界点も考慮に入れる必要があります。
ユーザーの深層心理を探る「インタビュー調査」
インタビュー調査は、調査員が対象者と1対1(デプスインタビュー)または複数人(グループインタビュー)で対話しながら、ブランドに対する意識やイメージを深掘りしていく定性的な調査手法です。
選択式のアンケート調査ではわからない「なぜそう思うのか」といった背景や理由、潜在的なニーズを探るのに適しています。
ブランドイメージの具体的な内容や、ブランドとの情緒的な結びつきなどを詳しく知りたい場合に有効です。
多くのサンプルを集めるのには不向きですが、量的なデータでは得られない深い洞察を得られる可能性があります。
特定エリアの生活者を対象にする「街頭調査」
街頭調査は、駅前や商業施設周辺など、特定の場所で通行人に対して直接声をかけ、その場でアンケート調査に協力してもらう手法です。
特定の地域や店舗周辺の生活者に限定して認知度を測定したい場合に有効な手段となります。
例えば、新店舗のオープン後やエリア限定のキャンペーン実施後などに、その地域での効果を測定する目的で活用されます。
その場で製品サンプルを試してもらいながら感想を聞くといったことも可能です。
ただし、回答者の属性に偏りが生じやすく、天候に左右されるといった側面も持ち合わせています。
【設問例あり】認知度調査で聞くべきアンケート項目
効果的な認知度調査を行うためには、アンケートの設問設計が極めて重要です。
単に認知の有無を問うだけでなく、「どのように知ったのか」「どのようなイメージを持っているのか」「購入したいと思うか」といった多角的な質問を組み合わせることで、ブランドの現状をより深く理解できます。
ここでは、認知度調査で一般的に用いられる質問項目を、具体的な設問例とともに紹介します。
これらの例を参考に、自社の調査目的に合わせたアンケートを作成してください。
ブランドの認知度を測るための質問
ブランド認知の広さと深さを測定するために、「純粋想起」と「助成想起」をそれぞれ測る質問を設けます。
純粋想起を問うには、「『(商品カテゴリ名)』と聞いて、思い浮かぶ企業名やブランド名を思いつく順にすべてお書きください」といった自由記述形式の質問が有効です。
一方、助成想起は、「以下の企業名やブランド名のうち、ご存知のものをすべてお選びください」のように、競合他社を含むブランドリストを提示し、選択してもらう形式で質問します。
この2つの質問により、認知度のレベルを定量的に評価することが可能になります。
ブランドを知ったきっかけ(認知経路)を特定する質問
消費者がどのようなチャネルを通じてブランドを認知したかを把握することは、今後のマーケティングコミュニケーション戦略を最適化する上で非常に重要です。
具体的な設問例としては、「〇〇(ブランド名)を、あなたはどこで知りましたか。あてはまるものをすべてお選びください」といった形式が挙げられます。
選択肢には、「テレビCM」「新聞・雑誌広告」「Webサイト・Web広告」「SNS(Instagram,Xなど)」「家族・友人からの口コミ」「店頭で見て」など、想定されるあらゆる顧客接点を網羅的にリストアップします。
これにより、効果の高い情報発信チャネルを特定できます。
ブランドに対して抱いているイメージを確認する質問
ブランドが消費者にどのようなイメージを持たれているかを把握し、企業が意図するブランドイメージとの間にギャップがないかを確認します。
この質問には、「〇〇(ブランド名)について、どのようなイメージをお持ちですか。あてはまるものをすべてお選びください」という形式で、複数のイメージワード(例:「高級感がある」「革新的」「信頼できる」「親しみやすい」など)を提示する手法が一般的です。
また、「〇〇(ブランド名)と聞いて、自由に連想する言葉やイメージをお書きください」といった自由記述形式の質問を設けることで、よりリアルな消費者の認識を探ることもできます。
購入意向や利用経験を探る質問
ブランドの認知が、実際の購買行動にどの程度結びついているか、あるいは結びつく可能性があるかを測ることも重要です。
まず、「あなたは〇〇(ブランド名)の商品を購入、またはサービスを利用したことがありますか」と利用経験を尋ねます。
その上で、未利用者や利用者全員に対して「あなたは今後、〇〇(ブランド名)の商品を購入、またはサービスを利用したいと思いますか」と問い、5段階評価(例:「ぜひ利用したい」~「全く利用したくない」)などで回答を求めます。
これにより、認知しているだけの層と、将来的な顧客となりうる層を区別して分析することができます。
効果的なブランディング調査を行うための4つのポイント
有益な示唆を得られるブランディング調査を実施するためには、計画段階でいくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
単にアンケート調査を行うだけでは、信頼性や妥当性の低いデータしか得られず、かえって意思決定を誤らせる原因にもなりかねません。
調査の精度を高め、結果を戦略に活かすためには、目的の明確化、対象者の適切な選定、比較対象の設定、そして継続的な実施という4つの視点が不可欠です。
調査の目的とターゲットを明確に定義する
ブランディング調査を始める前に、まず「この調査で何を明らかにしたいのか」という目的を具体的に設定することが最も重要です。
例えば、「新商品の市場投入にあたりターゲット層での認知度を把握したい」「リブランディング後のイメージ変化を測定したい」など、目的が明確であれば、必要な質問項目や適切な調査対象者も自ずと定まります。
同様に、調査対象となるターゲット層の定義(年齢、性別、価値観、ライフスタイルなど)も詳細に行うことで、アンケート調査から得られるデータの精度が向上し、より的確な分析が可能になります。
回答者に偏りが出ないように対象者を選ぶ
調査結果が市場の実態を正しく反映するためには、回答者の属性に偏りがないようにサンプリングを行う必要があります。
例えば、特定の年齢層や性別の意見に偏ってしまうと、得られたデータは全体の縮図とは言えなくなります。
これを避けるため、実際の市場の人口構成比に合わせて、年齢や性別、居住地などの割り付けを行うのが一般的です。
信頼できるアンケート調査会社は、質の高いモニターパネルを保有しており、こうした精緻な対象者選定に対応することが可能です。
比較対象として競合ブランドを設定する
自社ブランドの認知度やイメージに関するスコアを単独で得ても、その数値が高いのか低いのかを客観的に評価することは困難です。
市場における自社の立ち位置を相対的に把握するために、主要な競合ブランドをいくつか選定し、自社と全く同じ質問項目で調査することが極めて重要となります。
競合と比較分析を行うことで、自社の強みや弱み、独自のポジションが明確になり、今後の戦略を立てる上での具体的な課題や方向性が見えてきます。
どのブランドを競合として設定するかは、調査の目的に応じて慎重に選ぶ必要があります。
一度だけでなく定期的に調査を実施する
市場環境、競合の動向、そして自社のマーケティング活動によって、ブランドの認知度は常に変化します。
そのため、ブランド調査は一度きりで終わらせるのではなく、定点観測として継続的に実施することが望ましいです。
半年に一度、あるいは年に一度など、定期的に同じ設計でアンケート調査を行うことで、認知度やブランドイメージの推移を時系列で追跡できます。
これにより、自社のブランディング活動の成果を長期的な視点で評価したり、市場の変化をいち早く察知して戦略を修正したりすることが可能になります。
調査結果をブランディング戦略に活かす方法
認知度調査は、データを集めて分析するだけで終わりではありません。
その結果から得られたインサイトを、具体的なブランディング戦略やマーケティング施策に落とし込むことが最も重要です。
調査結果は、自社ブランドが抱える課題を明確に示してくれます。
例えば、認知度が低いのか、イメージが悪いのか、それとも競合に埋もれているのか。
課題に応じて、認知拡大や認知度向上に向けた適切な打ち手は異なります。
ここでは、調査結果の典型的なパターンに応じた活用例を3つ紹介します。
【活用例1】認知度が低い場合は、まず知ってもらう施策を強化する
調査結果から、ターゲット層における助成想起率、純粋想起率ともに低いことが明らかになった場合、最優先すべき課題はブランドの存在を広く知らせることです。
この段階では、ブランドの深い理解を促すよりも、まず「知ってもらう」ための施策に注力します。
テレビCMやWeb広告などの広告出稿量を増やしたり、インフルエンサーを活用したSNSでの情報発信を強化したりと、ターゲット顧客との接触機会(タッチポイント)を最大化するコミュニケーションが有効です。
認知拡大をKPIに設定し、リーチの広さを重視したメディアプランを策定します。
【活用例2】認知されていてもイメージが悪い場合は、訴求内容を見直す
ブランド名は知られているものの、企業が意図しないネガティブなイメージを持たれていたり、あるいは「特にイメージがない」という無関心層が多かったりする場合、単に露出を増やすだけでは問題は解決しません。
このケースでは、コミュニケーションの「量」ではなく「質」に課題があると考えられます。
ブランドが伝えたい価値やメッセージが消費者に正しく伝わっているか、広告クリエイティブやウェブサイト、SNSでの発信内容を根本から見直す必要があります。
ブランドの魅力を再定義し、ターゲットの心に響く訴求方法を開発することが求められます。
【活用例3】競合に比べて想起率が低い場合は、差別化ポイントを明確にする
ブランドの存在は知られている(助成想起率は高い)ものの、特定の利用シーンで最初に思い出してもらえない(純粋想起率が競合より低い)という課題もよく見られます。
これは、ブランドに独自性がなく、競合その他大勢の中に埋もれてしまっている状態を示唆します。
この状況を打開するには、競合ブランドにはない自社だけの強み(USP:Unique Selling Proposition)を明確にし、それを一貫性を持って伝え続けることが不可欠です。
「〇〇といえば自社ブランド」という強力な結びつきを消費者の心の中に築くため、差別化ポイントを軸にしたコミュニケーション戦略で認知度向上を図ります。
まとめ
ブランディング調査における認知度調査は、自社ブランドの現在地を客観的に把握し、未来の戦略を描くための羅針盤となる重要な活動です。
調査の目的を明確にし、純粋想起や助成想起といった適切な指標を用いて、信頼性の高いアンケート調査を設計することが成功の鍵を握ります。
また、一度きりの調査で終わらせず、定期的に実施して変化を追うことで、マーケティング活動の効果を測定し、戦略を常に最適化していくことが可能です。
調査から得られたデータを正しく解釈し、具体的なアクションプランに繋げることで、ブランド価値の継続的な向上を実現できます。