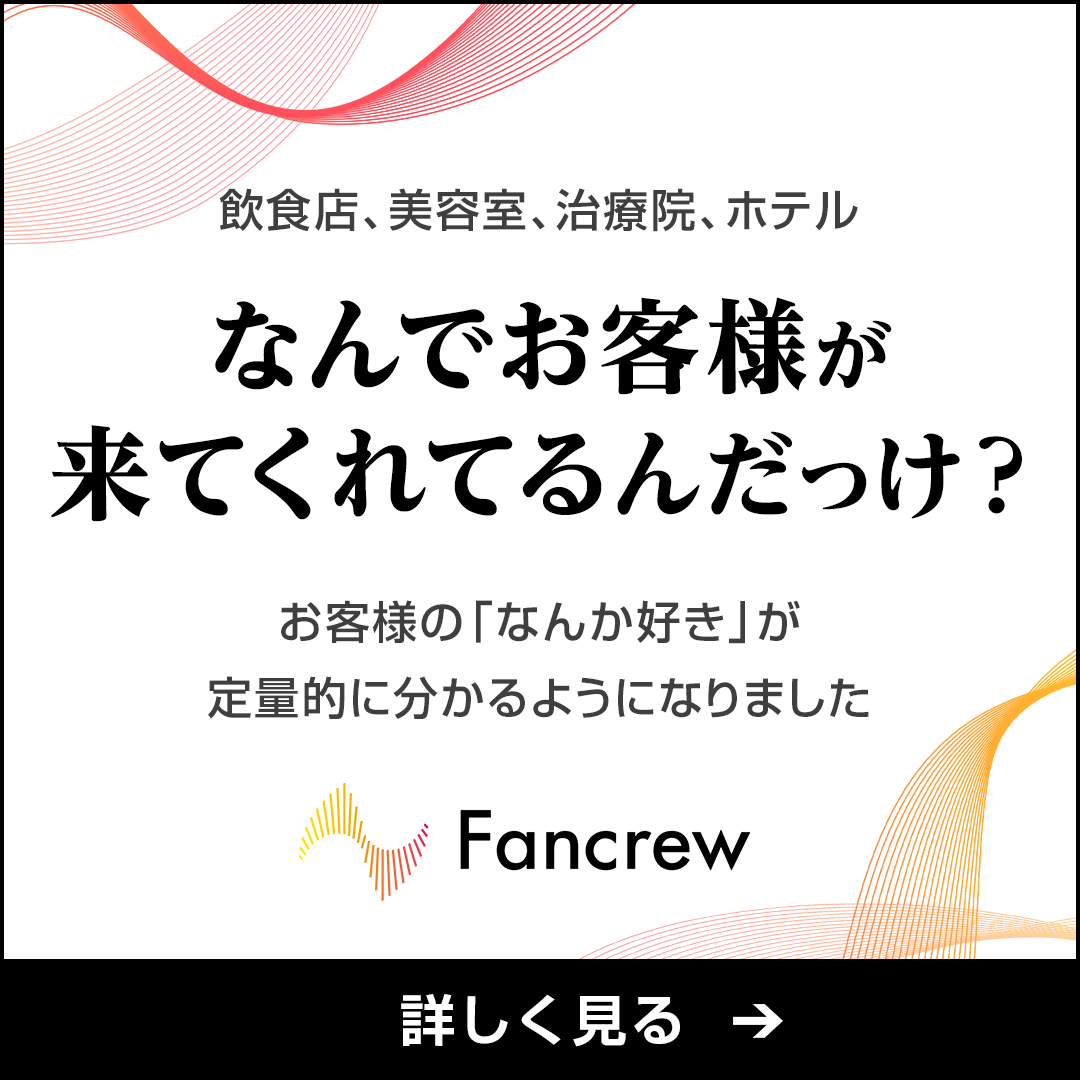顧客体験(CX)とは、商品やサービスの認知から購入、利用後のサポートに至るまで、顧客が企業と関わる中で得るすべての体験を指します。
本記事では、CXの基本的な意味から、マーケティングにおいてなぜ顧客体験の向上が重要なのかを解説します。
この記事では具体的な企業の成功事例や改善ステップ、AIなどを活用した未来のトレンドも紹介し、CX向上を目指すための網羅的な情報を提供します。
そもそも顧客体験(CX)とは?基本的な意味を解説
顧客体験(CX)とは、顧客が商品やサービスを認知し、購入を検討、利用、そしてアフターサポートを受けるまでの一連のプロセスで経験する、物理的・感情的な価値の総体を意味します。
これは単発の顧客満足度とは異なり、長期的な関係性の中で構築されるものです。
特定の製品利用時の操作性などを指すユーザー体験(UX)は、顧客体験を構成する要素の一つという定義になります。
つまり、UXは部分的な体験であり、CXは顧客と企業との関わり全体を通した包括的なユーザー体験を指す概念です。
なぜ今、顧客体験(CX)の向上がビジネスで重要視されるのか
なぜ現代のビジネスにおいて、顧客体験(CX)の向上が企業の重要な経営戦略として位置づけられるのでしょうか。
その背景には、市場の成熟化やデジタル化の進展があります。
機能や価格だけでの差別化が困難になった現代において、優れた顧客体験の提供は、顧客ロイヤルティを高め、継続的な関係を築く上で不可欠です。
企業がCX向上に取り組むことで得られるメリットは大きく、ブランド価値の向上やLTV(顧客生涯価値)の最大化につながります。
顧客との接点が多様化・複雑化しているため
スマートフォンの普及に伴い、顧客はWebサイト、SNS、実店舗、アプリなど、多様なチャネルを通じて企業と接点を持つようになりました。
これにより、顧客の購買に至るまでの行動は一層複雑化しています。
このような状況で一貫性のある優れた体験を提供するためには、オンラインとオフラインの垣根を越えて顧客にアプローチするオムニチャネル戦略が求められます。
個別のチャネルを最適化するだけでは不十分であり、すべての接点における体験を統合し、どのチャネルでも質の高いサービスを提供することが顧客ロイヤルティの向上に不可欠です。
顧客が体験する一連の流れを俯瞰し、全体として最適な体験を設計する必要があります。
消費者の価値観が「モノ」から「コト」へシフトしたため
現代の消費者は、単に商品を所有する「モノ消費」から、その商品やサービスを通じて得られる特別な体験や感動といった「コト消費」へと価値観をシフトさせています。
製品の機能的な価値だけでなく、購入プロセスにおける高揚感や、利用時に得られる満足感といった感情的な価値が購買決定に大きな影響を与えるようになりました。
顧客の深層心理にあるニーズを的確に捉え、期待を超える感動的な体験を提供することが、他社との強力な差別化要因となります。
この価値観の変化に対応できなければ、顧客から選ばれにくくなるため、企業にとって体験価値の創出は重要な経営課題です。
サブスクリプション型ビジネスが普及したため
近年、継続的にサービスを提供し月額料金などを受け取るサブスクリプション型のビジネスモデルが広く普及しました。
このモデルでは、一度きりの販売で利益を上げるのではなく、顧客にサービスを長く利用してもらうことで収益が安定します。
そのため、新規顧客の獲得以上に、既存顧客の解約を防ぎ、リピーターになってもらうことが極めて重要です。
契約後の顧客がサービスを最大限に活用し、成功体験を得られるように能動的に支援するカスタマーサクセスの考え方も、この文脈で注目されています。
契約後の顧客体験をいかに向上させ、顧客との長期的な関係を構築できるかが、ビジネスの成否を分ける鍵となります。
顧客体験(CX)を向上させるための5つのステップ
顧客体験を高めるためには、場当たり的な改善施策ではなく、体系的なアプローチが不可欠です。
顧客体験を向上させるプロセスは、現状把握から課題の特定、施策の実行と検証まで、大きく5つのステップに分解できます。
これらの要素を順に実行し、顧客視点で一連の体験を設計することで、効果的な改善活動を推進することが可能になります。
ここでは、その具体的な手順について解説します。
ステップ1:顧客との接点(タッチポイント)をすべて洗い出す
顧客体験を改善するための最初のステップは、顧客が自社の商品やサービスと関わる可能性のある全ての接点(タッチポイント)を網羅的にリストアップすることです。
具体的には、
- SNS広告
- Webサイト
- ECサイトでの購入
- 実店舗での接客
- 営業担当者との商談
- 購入後のコールセンターへの問い合わせ
- 製品やサービスの利用時
など、認知から購買、アフターサポートに至るまでのあらゆる場面が対象となります。
これらの接点を時系列で整理することで、顧客がどのような経路をたどって自社と関わっているのか、その全体像を客観的に把握することが可能になります。
この洗い出し作業の精度が、後の分析の質を大きく左右します。
ステップ2:カスタマージャーニーマップで顧客の感情を可視化する
洗い出したタッチポイントを時系列に沿って配置し、顧客が各接点でどのような行動を取り、何を考え、どう感じるかを一枚の図にまとめたものがカスタマージャーニーマップです。
このマップを作成することで、顧客の行動や思考、感情の起伏を具体的にイメージできるようになります。
顧客の視点に立って、サービス認知から利用後に至る一連の体験を旅(ジャーニー)のように捉え、企業側の思い込みではなく、顧客が実際にどのような体験をしているかを深く理解することが目的です。
どの段階で満足度が高まり、どの部分で不満を感じやすいのか、体験の全体像を可視化する上で非常に有効な手法です。
ステップ3:NPS®︎などの指標を用いて現状を正確に把握する
カスタマージャーニーマップによって可視化した顧客体験の仮説が、実際の顧客にどのように評価されているかを客観的なデータで把握します。
そのために、NPS®(ネット・プロモーター・スコア)のような顧客ロイヤルティを測定する指標を用いたアンケート調査を実施することが有効です。
この調査では、「この企業やブランドを友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか?」といった質問を通じて、顧客の推奨度を数値化します。
これにより、各タッチポイントにおける満足度や課題を定量的に評価し、マップ上で描いた仮説と実際の顧客の声との間に存在するギャップを確認することが可能です。
NPS®(ネットプロモータースコア)とは?顧客満足度との違いとアンケート調査方法・指標を解説
ステップ4:各接点における課題を特定し、優先順位を決める
アンケート調査やデータ分析の結果をもとに、顧客体験を低下させている具体的な課題を特定します。
特にNPS®︎のスコアが悪いタッチポイントや、顧客が離脱する原因となっている箇所を重点的に分析し、問題点を洗い出します。
例えば、「ウェブサイトの操作性が悪い」「問い合わせへの回答が遅い」といった具体的な課題が明らかになるかもしれません。
特定した課題のすべてに一度に取り組むことは非現実的なため、事業への影響度や改善にかかるコスト、実現性などを総合的に評価し、取り組むべき課題の優先順位を決定します。
最も顧客体験の低下に寄与している根本的な課題から着手することが、効率的な改善活動の鍵です。
ステップ5:改善策の仮説を立て、実行と検証を繰り返す
優先順位の高い課題に対して、「もし〇〇を改善すれば、顧客体験が向上するのではないか」という具体的な改善策の仮説を立てます。例えば、「ウェブサイトの購入手続きを簡素化すれば、購入完了率が向上する」といった仮説です。
この仮説に基づき、新しいサービスや仕組みを設計・導入し、実際に顧客へ提供します。
施策を実行した後は、再びアンケート調査やデータ分析を行い、改善効果を定量的に検証することが重要です。
期待した効果が得られなかった場合はその原因を分析し、新たな仮説を立てて次の施策を実行します。
この一連のサイクルを継続的に回し、組織全体で顧客体験の変革に取り組む姿勢が求められます。
【業界別】顧客体験(CX)向上のマーケティング成功事例
顧客体験の向上は、業界を問わず企業の成長に不可欠な要素となっており、売上向上や顧客ロイヤルティの獲得に結びついた成功事例も数多く存在します。
ここでは、小売、金融、飲食といった異なる業界の例を取り上げ、各企業がどのような課題に対し、いかなる施策で顧客体験を改善したのかを紹介します。
これらの具体的な取り組みは、自社のマーケティング活動を考える上での有益なヒントとなるでしょう。
小売業界:オンラインとオフラインを融合させた購買体験の提供
あるアパレル企業では、ECサイトと実店舗の顧客データを一元管理し、オンラインとオフラインを融合させたシームレスな購買体験を提供しています。
例えば、ECサイトで気になった商品を店舗で試着予約できるようにしたり、店舗スタッフが顧客のオンラインでの閲覧履歴や購入履歴を参考に、よりパーソナライズされた接客を行ったりします。
このような取り組みは、顧客がチャネルを意識することなく、自身の都合に合わせて最適な方法で買い物を楽しめる環境を創出します。
結果として、顧客体験(CX)だけでなく、従業員体験(EX)の向上にも寄与し、顧客満足度と売上の双方を高めることに成功しています。
金融業界:アプリ活用による手続きの簡略化とパーソナライズ
ある大手銀行では、スマートフォンアプリを中心としたデジタル戦略によって顧客体験を大きく向上させました。
従来、窓口で長時間待つ必要があった口座開設や住所変更などの各種手続きをアプリ上で完結できるようにし、顧客の利便性を飛躍的に高めました。
さらに、AWSなどのクラウド基盤を駆使して膨大な顧客データをリアルタイムで分析し、個々の取引状況やライフステージに応じた金融商品をアプリ上で提案するパーソナライズ施策を展開しています。
これにより、煩雑で時間がかかるという金融機関への固定観念を払拭し、顧客とのエンゲージメントを強化することに成功しました。
飲食業界:モバイルオーダーによる待ち時間短縮と快適な店舗体験
大手コーヒーチェーンでは、公式アプリを通じたモバイルオーダー&ペイシステムを導入し、顧客体験を劇的に改善しました。
顧客は来店前にスマートフォンで商品を注文し、決済まで済ませられるため、レジに並ぶことなくスムーズに商品を受け取ることが可能です。
この仕組みは、特にランチタイムなどの混雑時における顧客の待ち時間を解消し、快適な店舗体験の提供に大きく貢献しています。
また、従業員側もレジ業務の負担が軽減され、より質の高い接客や商品提供に集中できるようになりました。
このようなデジタル技術の活用は、顧客と従業員の双方にとってメリットをもたらし、良い顧客体験の創出につながっています。
AI活用が鍵?顧客体験(CX)の未来と最新トレンド
テクノロジー、特にAIの進化は、顧客体験のあり方を根本から変えようとしています。
AIの活用は、今後のCX戦略を立案する上で避けては通れない要素です。
AIチャットボットによる顧客サポートの24時間化や、膨大なデータ分析に基づく高度なパーソナライゼーションなど、未来の顧客体験を形作る最新のトレンドは、企業と顧客の関係をより密接なものへと導く可能性を秘めています。
AIチャットボットによる24時間365日の顧客サポート
AI技術を搭載したチャットボットを導入することで、企業は24時間365日、顧客からの問い合わせに対応できる体制を構築できます。
従来のシナリオに沿って応答するタイプに加え、近年では生成AIを活用した高性能なチャットボットも登場しています。
これにより、より人間らしい自然な対話で複雑な質問にも的確に回答し、顧客の自己解決率を高めることが可能です。
人間によるサポートが必要な場合は、問い合わせ内容を要約して適切な担当者へスムーズに引き継ぐことで、サポート業務全体の効率化と顧客満足度の向上を両立させます。
時間や場所を問わず、顧客の疑問を即座に解消できる環境は、顧客体験を大きく向上させます。
データ分析に基づくパーソナライズされた提案の高度化
AIは顧客の購買履歴やウェブサイト上での行動ログ、問い合わせ履歴といった膨大な非構造化データを高速かつ高精度に分析する能力に長けています。
この高度な分析能力を活用することで、企業は顧客一人ひとりの興味関心や潜在的なニーズを深く理解し、最適なタイミングでパーソナライズされた商品や情報を提供できるようになります。
例えば、ある顧客が特定の商品を閲覧した数日後に、関連商品の割引クーポンを自動で配信するといった施策が可能です。
このようなきめ細やかなアプローチは、顧客に「自分のことを理解してくれている」という特別感を与え、ブランドへのロイヤルティを高めます。
VR/AR技術を活用した新しい購買体験の創出
VR(仮想現実)やAR(拡張現実)といったデジタル技術は、これまでにない革新的な購買体験を創出する可能性を秘めています。
例えば、家具の購入を検討している顧客が、スマートフォンのカメラを通して自宅の部屋に実物大のデジタルな家具をARで配置し、サイズ感や部屋の雰囲気との相性を購入前に確認できるサービスがあります。
また、アパレル業界では、仮想空間上で自身のアバターに服を試着させるVRストアも登場し始めています。
これらの技術は、オンラインショッピングの利便性と、実店舗でのリアルな体験価値を融合させ、物理的な制約を超えた新しい顧客接点を生み出します。
まとめ
顧客体験の向上は、一度きりの広告キャンペーンとは異なり、組織全体で長期的に取り組むべき経営課題です。
顧客とのあらゆる接点を洗い出し、データに基づいて改善のサイクルを回し続けるプロセスが不可欠となります。
他社の成功事例などを参考にしつつも、最終的には自社の顧客を深く理解することが最も重要です。
関連するセミナーやイベントへの参加、あるいは社内研修の実施を通じて、従業員一人ひとりの顧客体験に対する意識を高めることも有効な手段です。
顧客体験という視点を事業活動の根幹に据えることで、持続的な成長を実現することが可能になります。